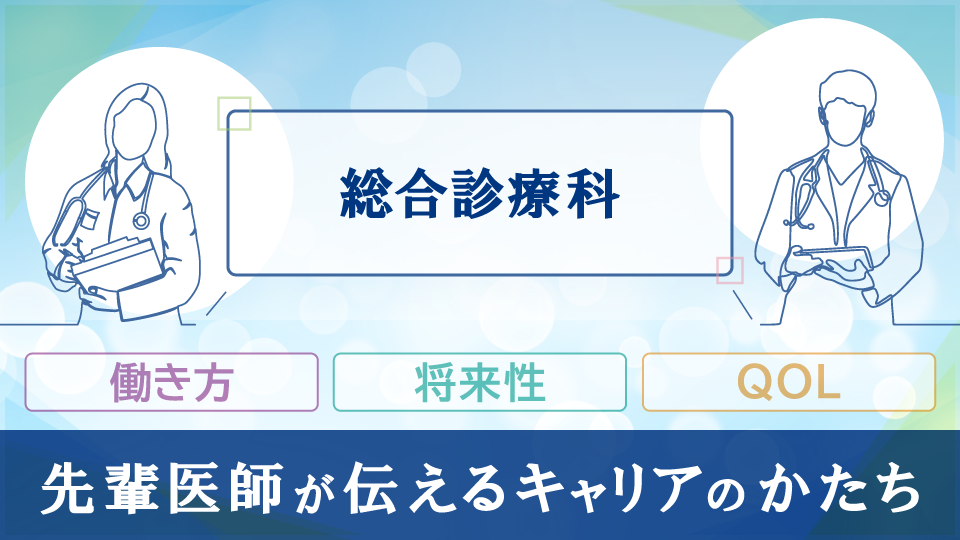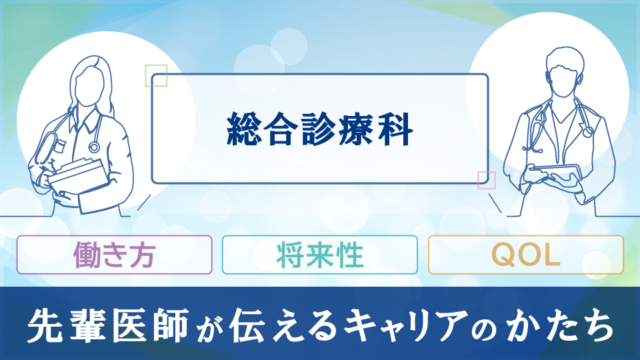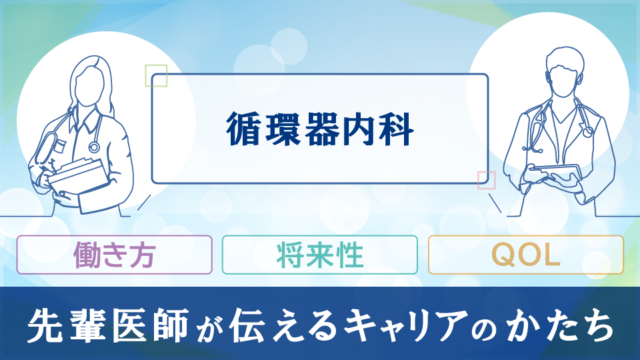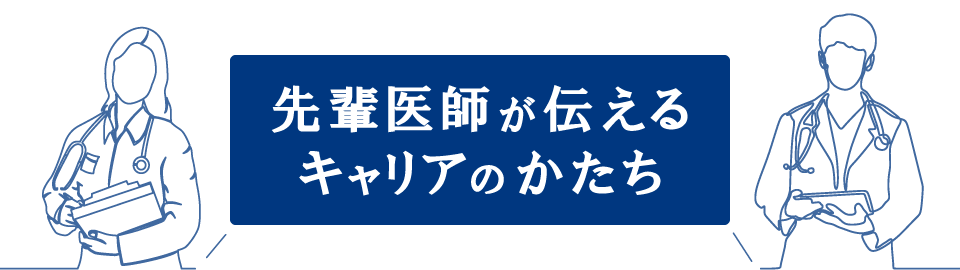
患者の人生に寄り添う総合診療の魅力に惹かれ、教育や研究にも挑戦しながらキャリアを築く若手医師にお話を伺いました。 研修での悩みや乗り越えた経験、働き方の工夫からは、これからの医師人生を考えるうえでの気づきが得られます。
医師プロフィール 2019年 医師免許取得/家庭医療専門医資格を取得中/高齢者が多い地域での研修を通じて、患者の背景も含めて診る総合診療に魅力を感じ志望/現在は亜急性期〜慢性期病院に勤務しながら大学院にも通い、教育・研究にも取り組む/初期研修での経験を糧に、患者にとってより良い医療を考えていく姿勢を大切にしている
総合診療科について、どこに魅力を感じたか教えてください
初期研修の基幹病院は、高齢者が多いエリアにありました。超高齢社会となる中で、人生の最終段階まで見据えた長期スパンで、Bio-Psycho-Socialの観点から複合的に診ていく医師の必要性を痛感しました。
そんななか、教育病院の総合診療科で研修機会があり、各専門科のポケットに落ちている患者を診ている先生方に出会い、その教育的な姿勢とBioは当然診た上で、背景を含め、落ち着きどころ、いい塩梅を患者さんや家族、他職種と連携しながら探していく姿に共感しました。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
総合診療科の後期研修プログラムとしては、小児科や救急研修が必須となります。いわゆるホームとなる総合診療科外で、初期研修とも、専門科の後期研修とも違う立場で研修するため、目標の置き方や各指導医の理解を得ていくのに時間を要しました。また、初期研修の頃よりは各診療科で長く研修するため、人間関係のトラブルに苦労したこともありました。
一方、総合診療科では元々教育的な先生方が多いこともあり、診療自体については大きなストレスなく過ごすことができました。ただし、教育Dutyも多く、カバーする疾患範囲が広い分、自分に自信がないなかで初期や学生を教育することには難しさを感じました。
現在のワークライフバランスについて教えてください
現在所属している病院は亜急性期〜慢性期病院であり、結婚・出産を経た女性医師も多く、ワークライフバランスは比較的取りやすい環境です。一方で小規模なため、急性期病院のような当直明けの早上がり、は実現されていません。
また、後期研修の傍らで大学院(博士課程)も通学しています。 COVID-19の影響でほぼオンライン授業だった上に、職場も教育的な側面に対する理解があるため、年数回程度の休み(対面授業等)には協力してもらえました。
先生がいま考えている今後のキャリアパスを教えてください
今後も亜急性期〜慢性期病院での勤務を続けたいと考えています。性格的にも、臨床能力的にも超急性期病院は向いていないと感じることと、何らかの形で教育や研究も継続していきたいため、今のプログラムの指導医として残るのが自信をつけるうえでもよい選択と感じています。
一方で、同じ組織に居続けるのも望ましくないと思うので、病院規模や職務は大きく変えずに、転職の機会を探っていく予定です。
初期研修での失敗談と、それをどう活かしているか教えてください
小規模病院での当直中(研修医1名+指導医1名、看護師以外のコメディカルはオンコール体制)に指導医や待機のコメディカルが緊急処置に入ってしまい、しばらく一人で救急患者を診ることとなりました。(患者を帰す前には一報する前提)
そんななか、虫垂炎が否定できない腹痛患者が来院したものの、検査技師の追加オンコールを呼ぶ判断ができず、ピリついた処置室で、身体所見のみ・検査なしのぼろぼろのプレゼンをするはめに。。。指導医に「なんで検査してないの?」と詰められ、慌てて検査を追加することとなりました。(結局、虫垂炎ではありませんでした)
今は学年も上がったので、必要なときは必要、と言い切って検査をしていますが、周囲へ気を使いすぎるあまり、患者さんの利益を軽視しないように気をつけなければならないと思い知った経験でした。
地方と都市部で総合診療医に求められることはどう違いますか?
地方では特に専門科へのアクセスが悪く、普段の診療範囲を超えた治療や、専門科へ繋ぐまでの応急処置的な治療行為が必要となることがあります。一方で都市部では、専門科へのアクセスが容易な分、より早期に専門科への紹介が求められる傾向があります。
地方も都市部も変わらずに必要なこととしては、各専門科の間を埋め、身体的だけでなく、社会的に複雑な患者さんの診療を行うことです。
初期研修の2年間で必ず身につけておくべきことは何ですか?
各診療科のローテーションの中で、その科の先生が気にされるポイント(たとえば脳卒中時の最終健常時間など)を学んでいくと、後期研修以降の他科コンサルト時に役に立ちます。
また、どんな診療科に進むにしても、抗菌薬/輸液管理などは避けることができません。
このように、自分が進む診療科を想定して、各々の科で何を最低限自分は身につけたいのかを決めておくと、研修目標が定めやすいと思います。
後進の医師へアドバイスをお願いします
医師という仕事は、体力的にも精神的にも辛いことが多い職業です。しかし、患者さんの治療がうまくいったときの喜びはもちろんですが、患者さんの人となりを考慮して、Betterな道を共に考えていく経験は他の仕事にはないものだと思います。
低学年のうちは自信もなく、迷うことも叱られることも多いですが、一つ一つ積み重ねていくことで成長していくことができます。
自分の専門科はもちろん、他部署とも連携することで患者さんにとってのより良い治療を模索できるように、がんばってください。
コンサルタントに聞くことで開ける未来があります!