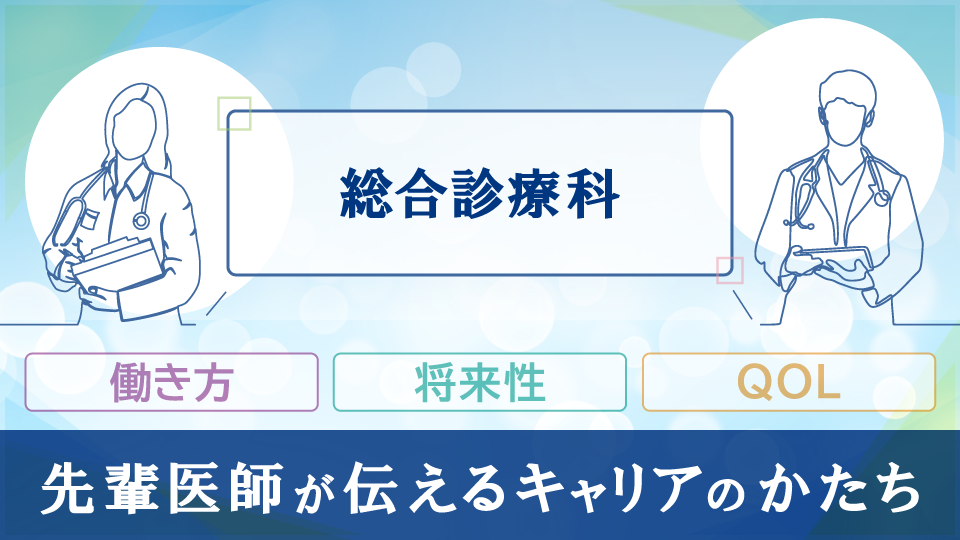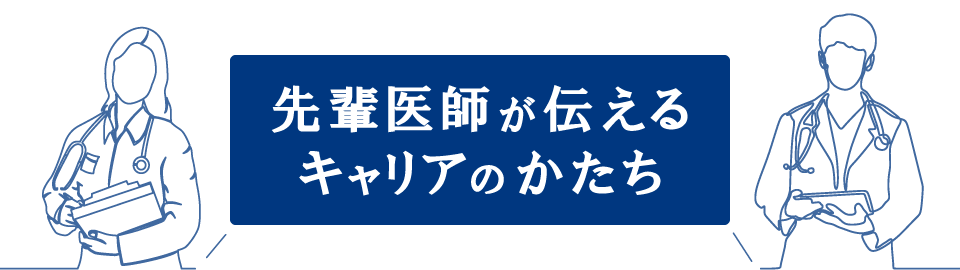
地域診療所での実習と育児を両立しながら、総合診療の現場で研鑽を積む男性若手医師にお話を伺いました。 キャリアの模索や働き方の工夫、在宅医療や病態生理への向き合い方など、診療科選びや今後の進路を考えるうえで多くの示唆を与えてくれる内容です。
医師プロフィール/羽角貴之先生
 2020年 医師免許取得/総合診療科専攻/地域診療所で実習中、育児と両立しながら研鑽中/病態生理から症状を読み解く診療アプローチに共感し、総合診療を志望/家庭医療・内科・リウマチ膠原病専門医を目指す2階建てキャリアを構築中/在宅医療や地域連携にも関心を持ち、患者の希望に寄り添う医療を実践したいと考えている
2020年 医師免許取得/総合診療科専攻/地域診療所で実習中、育児と両立しながら研鑽中/病態生理から症状を読み解く診療アプローチに共感し、総合診療を志望/家庭医療・内科・リウマチ膠原病専門医を目指す2階建てキャリアを構築中/在宅医療や地域連携にも関心を持ち、患者の希望に寄り添う医療を実践したいと考えている
総合診療科について、どこに魅力を感じたか教えてください
最も大きな理由は、総合診療科が私の理想とする医師像に近かったことです。
私は大学病院で初期研修を行い、2年目の途中まで進路を決めかねていました。専門医の先生方のプロフェッショナリズムに触れる機会が多かった一方で、限られた時間と資源の中では誰でも専門外の対応が難しいことがある現状も目にしました。
一方で、総合診療科の研修では、どのような患者さんの訴えに対しても、まずは真正面から受け止めて、「自分に何ができるか」を真剣に考えて、その上で専門医の先生と適宜連携しつつ対応する……そういった総合診療医の先生方の姿がありました。それを見て、「私がなりたかった医師とは、まさにこういう存在だった」と思い起こされたのを強く覚えています。
また、私自身が患者であったとしたら、総合診療科の先生のように、どんなことでも相談できて、誠実に答えてくれる医師に診てもらえることは非常に心強いと感じました。そうした先輩方や指導医への憧れが、総合診療科を志す決め手となりました。
加えて、奈良医大総合診療科で学んだ「病態生理から症状を解釈する」というアプローチは非常にユニークで、他の診療科ではあまり触れることのない考え方でした。この方法は患者さんにとっても納得感を得やすく、実際に先輩方や指導医の先生方がこのアプローチを用いて患者さんから厚い信頼を得ている姿を何度も目にしました。そのように「私も患者さんから信頼される医師になりたい」と強く感じたことも、総合診療科を志望した大きな理由の一つです。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
大きなイメージギャップはそれほどありませんでしたが、強いて挙げるとすれば、総合診療科はもともと「難しいことをしている大変な診療科」という印象を持っていたものの、実際にその中で働き始めてみると、想像以上にさらに難しく、大変な診療科であることを実感しました。
特に、学ぶべき内容が非常に多岐にわたっており、しかも高度化する現代医療の水準に追いつく必要もあるため、日々膨大な学習量が求められるという点で、予想を超える負荷を感じています。また、活躍を求められるフィールドも、大学病院から地域の診療所まで非常に幅広く、介護保険や診療報酬など、純粋に医学以外の知識も求められ、困惑することも決して少なくはなかったと思います。
一方で、その「学ぶ領域の広さ」は裏を返せば「何を学んでもよい」という柔軟な風土とも言え、これは私の(言葉は悪いですが気分任せの)気質に合っていると感じています。例えば、私は整形外科領域の知識に興味を持っていますが、仮に内科系の診療科で同じことをしていたら、眉を顰められることもあるかも知れません。しかし、総合診療科では内科以外の知識も非常に重要で、専門外の領域の知識を深めることを歓迎する雰囲気があると思います。このように自分の関心のある分野を追究できるという点で、学ぶ楽しさと自由さのある診療科だと感じています。
とはいえ、やはり学ぶべきことは多く、それが苦しく感じることもあります。指導医の先生方のおかげで、接遇や話し方の技術を身につけられた結果、患者さんに一定の満足感を得ていただきやすいように思います。しかしその一方で、その満足や信頼に甘えてしまいそうになる瞬間もあり、分からないことを取り繕ってしまう誘惑に駆られることもあると、自分自身で自覚しています。
ある指導医の先生の言葉で「総合診療科は、手を抜こうと思えば一番楽な科だけれども、本気でやろうとすれば一番難しい科だ」というものがありましたが、本当にそのとおりだと感じます。自分の中にある“楽をしたい”という気持ちと日々向き合いながらも、患者さんにとって最善の医療を提供するために、知識と技術の研鑽を続けなければならないと感じている毎日です。
現在のワークライフバランスについて教えてください
現在、私は地域の診療所で実習をしていて、上司に当たる診療所長の先生が非常に理解のある方で、私自身、1歳の息子の子育てを全力で楽しみながら、仕事と私生活の両立ができていると感じています。
ワークライフバランスと医療の両立は、昨今非常に大きな課題として取り上げられています。実際、子育てに参加することで勤務に制限がかかりますし、技術や知識を研鑽しなければならない医師という立場では、子育てに参加しにくい部分もあると思います。ただ総合診療という領域に進むのであれば、子育ては医師としての成長に確実につながると考えています。実際、息子が生まれて「親とは」「子供とは」ということへの理解が深まったことで、診療所に来られるお子さんや子育て世代の患者さんの気持ちを、より深く理解できるようになったと感じています。
日々の生活で育児にしっかりとコミットするという経験は、単に生活とのバランスを取るという以上に、医療の深みや共感力を高める貴重な機会になっていると感じます。
世間では男性の育児参加が進んでいる一方、医師の世界では一歩二歩遅れを取っている印象です。しかし総合診療という分野においては、育児経験を通じて得られる視点や共感が、他の診療科と比較して相対的にプラスに働く場面が多いと感じます。もし後輩の先生方が子育てをする機会があれば、ぜひ全力で関わっていってほしいです。
先生がいま考えている今後のキャリアパスを教えてください
私はまだしばらく地域枠の義務年限があるので、それまでは奈良県内の公的病院で勤務する予定です。その間に、専門医資格を積極的に取得していこうと思っており、現在の総合診療専門医研修が終了後は、いわゆる“2階建て”のキャリアとして家庭医療専門医の資格取得を目指します。さらにその後、内科専門医の資格を取得し、最終的にはリウマチ・膠原病内科専門医の取得にも挑戦したいと考えています。
博士号の取得についても現在検討中で、研修医の頃と比較して考えられないほど前向きに検討しているのですが、やはり育児中ということもあり、子供の成長や家庭の状況と相談かなと考えています。
最終的には、地域医療の現場において、これまでに培った専門性を活かしながら、総合診療の幅広い視点で患者さんと向き合い続けていきたいと考えています。地域に根ざし、在宅医療も含めた包括的な医療を提供し、患者さんの生活に寄り添う診療を実践できれば、と考えています。
初期研修での失敗談と、それをどう活かしているか教えてください
お看取りに至った症例で、強く心に残っている症例があります。ある終末期の方で、ご本人は一時的でも自宅に帰りたいと強く希望されていたものの、介護体制や経済面など複合的な問題を私が解決できず、残念ながら自宅退院はかないませんでした。しかし今であれば、在宅医療を担っている医療機関と連携して、ご本人の希望を叶えることができたかもしれないと感じています。
大学病院という現場は、在宅医療とどうしても距離があり、「在宅でできることが意外と多い」ということを伝えにくい現状があると思います。今後、私が医療機関同士の連携を円滑にするために動くことで、在宅医療についてより多くの先生方に知っていただき、患者さんの希望にかなう医療をより広く提供できるように貢献したいと考えています。
総合診療科を選んだタイミングとそのきっかけを教えてください
初期研修医2年目の夏頃だったと思います。もともと明確な志望科を持たずに初期研修を開始しており、地域枠の兼ね合いで進むことができる診療科が限られていました。現在でこそ外科に進むことは可能になっていますが、私のときは内科一般、小児科、救急科、麻酔科、総合診療科、精神科、産婦人科が候補であったと思います。研修を進める中で「内科系の診療科が良い」と感じ、内科を一通り回った後、「人と深く関われるところが良い」と考え、小児科とも迷いましたが、総合診療科に決めました。
きっかけとしては、前述の「何でも受け止める姿勢」「病態生理からのアプローチ」が非常に魅力的に感じたことももちろんですし、地域研修でハイレベルな在宅医療を目にして「独居でも穏やかな時間を最期まで過ごすことができるのか!」と感銘を受けたことも、大きなきっかけであったように感じます。
初期研修中にやっておくとよいことはありますか?
自戒を込めて、眼の前の症例にしっかり食らいつくこと……というのはもちろんですが、あくまで個人的には、ライフプランを煮詰めていき、必要に応じて人生のパートナーを見つけておくことをオススメしたいです。多くの人が後期研修を始めることになると思いますが、基本的に後期研修は負荷が強く、(じっくり子育てさせていただいている立場ですが)時間的・精神的にあまり余裕はありません。そんな中で人生のパートナーを見つけるのは、スケジュール的になかなか厳しいものがあると感じます。
もちろん、人生の過ごし方は人それぞれなのですが、後期研修が始まってからは時間の流れが矢のように早くなっていると感じています。加えて、年齢を重ねるごとに体力が落ちていく自覚もあり、さりとて子育てには膨大な体力を費やさざるを得ない現状もあります。そういった意味で、若いうちだから出来ることは確実にあるように思われますので、人生の優先順位を早めに明らかにして、それに向けて動き出す……というのを、初期研修中にやっておくことをお勧めします。
後進の医師へアドバイスをお願いします
総合診療科、良いですよ! オススメです。
総合診療科の研修プログラムには、地域医療を学ぶ期間が設けられており、主に診療所での業務を学ぶことが出来ます。研修先にもよりますが、へき地の診療所においては管理者としての業務を行うことがあり、診療所の役割について深く学ぶことが出来ます。もちろん、研修プログラムの指導医からフィードバックを受けることができますので、バックアップ体制が整っている中で診療所の責任者として働くことが可能です。これは他の内科系診療科の研修では真似できないことで、将来的に開業を考えている先生方には、非常にオススメできるポイントです。
加えて、総合診療科のフィールドは多岐にわたっており、上述の診療所から市中病院、大学病院に至るまで、幅広い場での活躍が求められます。そのため、ワークライフバランスに応じて柔軟に勤務形態を変更でき、結婚・子育てやご両親の健康など、個人ではコントロールが難しい人生のイベントにも対応しやすいのが、総合診療科を専攻する大きなメリットの1つです。
もちろん、習得すべき技能・知識が非常に多岐にわたることから、私自身も戸惑うこともありますが、身に付けたことが直に患者さんのためになることが多く、学習のモチベーションも(勉強嫌いの私にしては)高く保てているように感じます。また同時に、研修医の時点では明確な進路を見いだせない先生も、ひとまず総合診療科を専攻し、その中でやりたいことを見つけて軌道修正していく、という進路をとることも可能です。
もし進路が総合診療科以外の領域になったとしても、総合診療科で学んだことは無駄になることは決して無い、と言えるのも、総合診療科の強みだと思います。
時代のニーズとしても、総合診療医は広く求められている存在であることは間違いありません。ゆえに「どこでも」「いつでも」「どんな形でも」活躍でき、将来のライブイベントに合わせた働き方が、総合診療科では可能になります。和気あいあいとした雰囲気の先生が多い科でもあるので、ぜひご検討ください!
羽角貴之先生経歴
- 所属:奈良県立医科大学付属病院 総合診療科
- 出身地:千葉県
- 卒業大学:奈良県立医科大学
- 2020年 奈良県立医科大学附属病院(奈良県)初期研修
- 2022年 奈良県立医科大学付属病院 総合診療科(専攻中)
コンサルタントに聞くことで開ける未来があります!