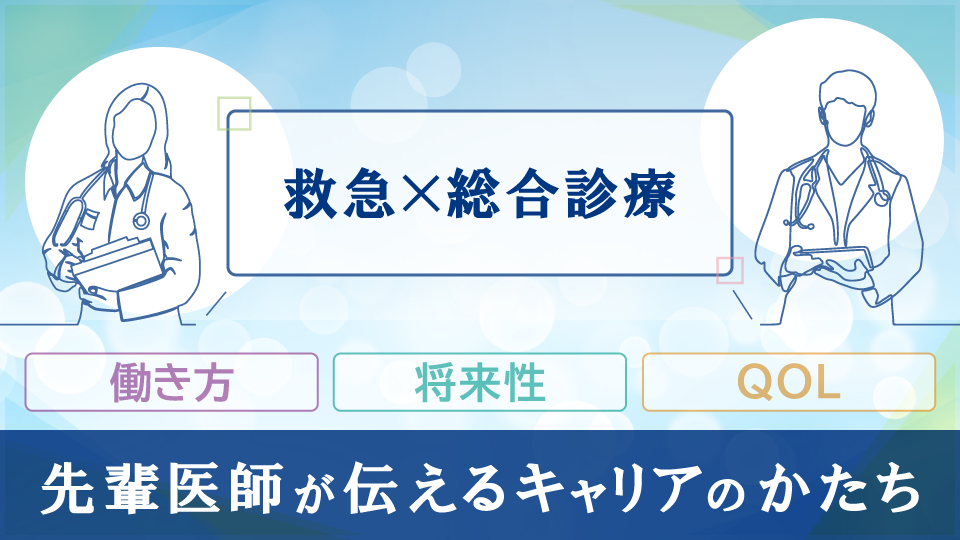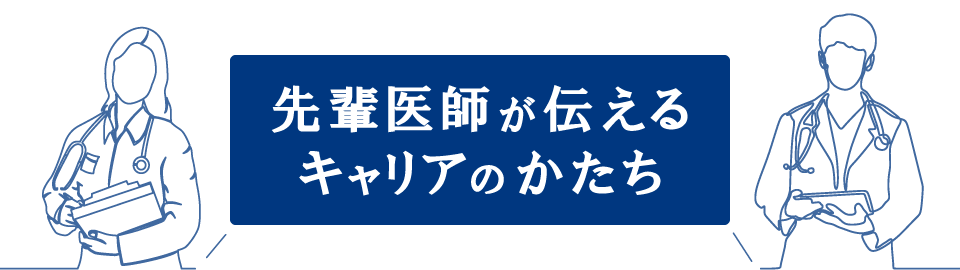
自分の苦手意識を原動力に、救急と総合診療の両分野でキャリアを築いてきた女性医師にお話を伺いました。離島勤務や子育て、地域活動を通じて見えてきた自分らしい医師としての在り方とは──。柔軟な働き方と深い専門性、その両立を通じて等身大の医療のかたちを築いています。
医師プロフィール/若林美帆先生
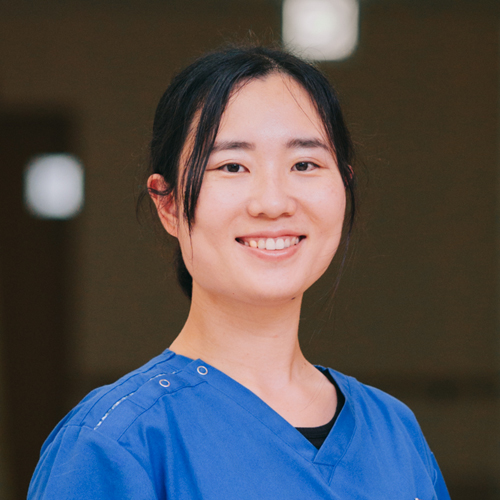 2016年 医師免許取得/救急科専門医資格を保有/離島勤務・地域活動・子育てを両立しながら、救急と総合診療の両分野で実践/ACPや地域医療への関心を持ち、ダブルボードを目指して研鑽中/若手医師の育成や柔軟な働き方の可能性を追求している
2016年 医師免許取得/救急科専門医資格を保有/離島勤務・地域活動・子育てを両立しながら、救急と総合診療の両分野で実践/ACPや地域医療への関心を持ち、ダブルボードを目指して研鑽中/若手医師の育成や柔軟な働き方の可能性を追求している
救急科について、どこに魅力を感じたか教えてください
初期研修のときに急変対応に携わる機会が多く、自分自身の力量不足を実感していました。
自分自身で命を救えなかったとしても、助けられる人につなぐ・家族や大切な人と過ごす最期の時間を作る・患者さん自身が大事な決断を行うことができるように助ける、といったことができるような力をつけたいと思い、選択しました。
また、私自身救急対応に苦手意識があったので、最終的に救急の世界に身を置くことがなかったとしても、自分自身で身に着けることが難しい救急の知識・技術を専門研修を受けることで習得したいという気持ちもありました。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
研修先の施設が丁寧に指導してくださったので、救急に苦手意識を持つ私でも救急対応が必要最低限行えるようになったので、「厳しい環境で手出しのできない世界」から「ふみこめば多少なりとも貢献できる世界」になったことが入職前後でのイメージの変化ではあります。
また、殺伐とした世界だと思い込んでいましたが、忙しかったり患者さんの状態が不安定で緊張感のある世界ではあるものの、患者さん・家族・スタッフ間で良好なコミュニケーションを築くことがいい意味でのギャップです。
ワークライフバランスについて教えてください
救急科に所属している時期はオンオフがはっきりしていたので、当直中眠れなかったとしても翌日しっかり休養を取ったりができたので比較的バランスがよかったと感じています。
またほかの施設で救急医が少ない現場だと日勤帯は救急医が対応し、夜間帯は全診療科で当直を組むこともあったので、救急医だから休みがない、という状況は直面せずにすみました。またICUは主治医の名前はついていますが基本的に勤務ごとに担当医が変わるため、休みの日の呼び出しがなく、休暇を休暇として過ごすことができたのも助かりました。
総合診療科について、どこに魅力を感じたか教えてください
私の思いとして「患者さん自身の望む最期を迎えてほしい」というものがあります。救急専攻医時代に、終末期の患者さんが救命救急センターに搬送され、人工呼吸管理等集中治療を受けICUで孤独に最期を迎えたという事例を経験しました。
当時担癌患者など一部の疾患群の方にACPの概念は浸透され、その方々は望まない胸骨圧迫や救命処置を受けずに最期をむかえられましたが、他の高齢者ではACPなどの話を共有できておらず、望まない搬送・救命処置を受ける方もいました。
ただ一方で救命処置を行うことで自宅で望んだ暮らしを過ごせている方も経験しました。なので、救命救急センターの外で、救急処置などのことを伝え、適切な方に適切な医療を届けられる立場になりたいと思いました。その中で、地域医療・総合診療の知識・経験が必要だと感じ、総合診療科と救急医のダブルボードを目指すことにしました。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
入職時と入職後のギャップはそこまでなく、自分の研鑽をつみたいと思ったことがたくさん経験できています。特に今所属している離島は僻地でなので自分自身が携わった患者さんや家族がそのまま自分の生活にかかわってくるので、非常にやりがいがあります。
また総合診療科は、医療機関内だけでなく地域活動も行っており、市民に教育を提供することで医学以外の方法から自分の診療の助けができることも魅力だと思います。
ワークライフバランスについて教えてください
今現在未就学児を二人育てながら、単身赴任で勤務しているため、勤務内容を調整してもらっています。当直等ができないのでそれ以外の形で病院に貢献させてもらってます。
外来・診療所・在宅診療を主にさせていただいているため、勤務時間外は子供との時間を過ごすことができています。また地域活動を子供と参加することで、市民とのつながりを強く持つことができていると思います。
先生がいま考えている今後のキャリアパスを教えてください
救急医をベースに、地域医療・総合診療領域の研修を積んでいます。今後近い将来医師のニーズとしては急性期病院で専門性を高める医師と地域に即した総合診療ができる医師の二極化が起きるのではないかと思っています。なので、急性期と地域をともに経験したことのある若手医師は非常に喜ばれると思っています。
今後自分自身の研鑽を積みつつ、近畿圏の都市部の若手医師が、研修元の医療機関と、山陰地域や現在勤務している離島の医療機関でともに診療の経験を積むことで、都会と僻地、救急と総合診療をともに経験したことのある若手の医師を育てていくお手伝いができたらと思っています。
初期研修での失敗談と、それをどう活かしているか教えてください
初期研修時代の急変対応は、なかなか自分自身上手に動けず、上級医へのコンサルテーションも苦手だったため、自分の中で内省する日々を過ごしていました。また、離島でも急変対応に直面し、自分の力量不足を強く実感しました。
そこでの経験が、「100%できないとしても、少しでも患者・家族の利益になるような救急対応を行う」という私のモットーの原点になっていると思います。
また、学生~初期研修時代に苦手だと思っていた診療科が「救急」「総合診療」で、積極的に診療に関わらなかったのはよくなかったと思います。
結果今新しい視野で取り組めているので、苦手だと思う診療科でもとりあえず取り組んでみるのが大事だと思います。
後進の医師へアドバイスをお願いします
私は初期研修開始時点では救急が一番苦手で、救急医になる未来は全く考えていませんでした。ただ、自分の思い描く医師像を実現するために必要なスキルが救急であったため、結果的に救急を専攻してよかったと思います。
最初に考えている診療科・進路が経過中に変わっていくことはよくあることだと思いますし、結果何かに貢献できているのならその時々に行っている診療・活動が正解なんだと思います。
ぜひ好きな道を進んでいただけたらと思います。
若林美帆先生経歴
- 所属:隠岐病院、総合診療科、医長
- 出身地: 大阪府
- 卒業大学:奈良県立医科大学
- 2016年 大阪市立総合医療センター(大阪府)初期研修
- 2018年 大阪市立総合医療センター 救急科プログラム(2021年度専門医取得)
- 2024年 耳原総合病院 救急総合診療科勤務
- 2025年 島根県立中央病院 総合診療プログラム
現在は離島研修にて、連携病院の隠岐病院へ所属
コンサルタントに聞くことで開ける未来があります!