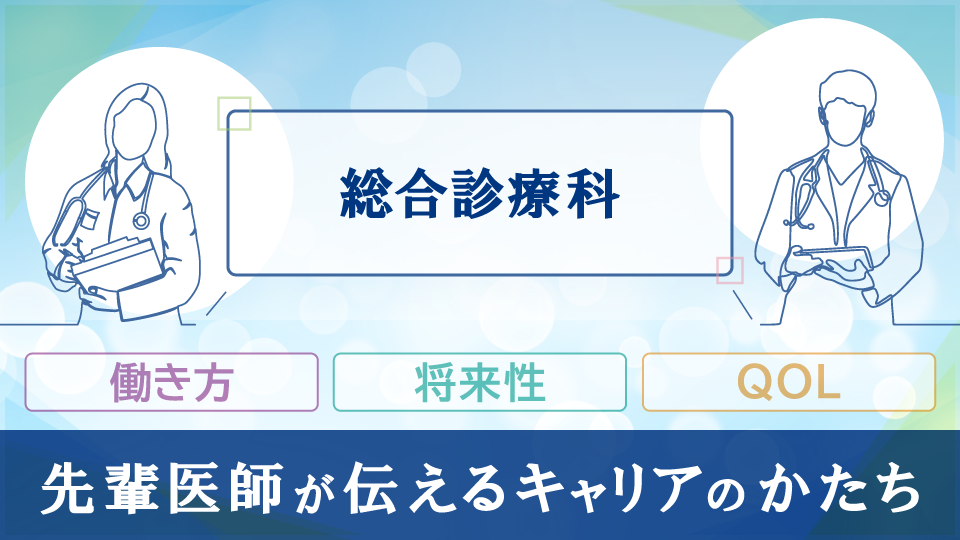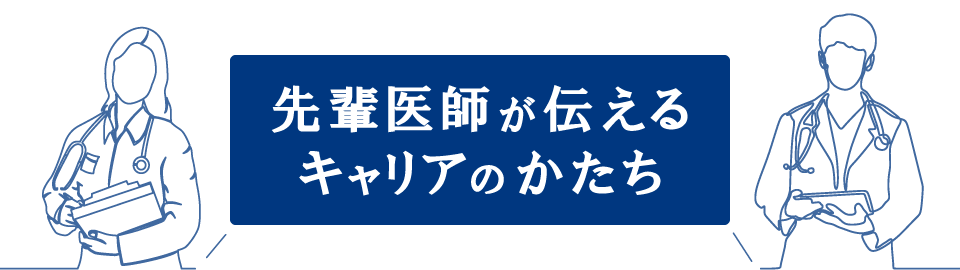
自分の興味やライフスタイルに合わせて、総合診療というフィールドでキャリアを築いてきた専門医にお話を伺いました。 多様な研修経験、海外での学び、教育・執筆活動などを通じて、柔軟かつ自分らしい働き方を実現してきたその歩みからは、総合診療の奥深い魅力と、広がるキャリアの可能性が見えてきます。
医師プロフィール/小林尭広先生
 2016年 医師免許取得/総合診療専門医資格、ECFMG Certificateを保有/大学病院、市中病院、診療所、小児科外来など多様な施設で研修を経験/
英国大学院にて家庭医療学修士課程を修了(オンライン)/
現在、在日米軍基地病院にてフェローとして勤務/
将来的には教育病院の関連クリニック勤務や海外研修も視野に柔軟な働き方とキャリアの多様性を活かし、総合診療の可能性を追求中
2016年 医師免許取得/総合診療専門医資格、ECFMG Certificateを保有/大学病院、市中病院、診療所、小児科外来など多様な施設で研修を経験/
英国大学院にて家庭医療学修士課程を修了(オンライン)/
現在、在日米軍基地病院にてフェローとして勤務/
将来的には教育病院の関連クリニック勤務や海外研修も視野に柔軟な働き方とキャリアの多様性を活かし、総合診療の可能性を追求中
総合診療科について、どこに魅力を感じたか教えてください
総合診療科の魅力は、その活躍のフィールドが本当に幅広いことです。 診療所・クリニックでのプライマリ・ケア、病院での臓器横断的なホスピタリスト業務、さらには地域によっては小児や産婦人科的ケアにも関わることができます。
地域のニーズに応じて自分自身をアップデートしていくことが求められる一方で、自分の関心にマッチした地域や病院を選んで働けるという自由さもあります。
学問的好奇心を持ちながら、ライフスタイルに応じた柔軟な働き方ができる点は、現代社会に非常に合っていると思います。
こうした点が、私が総合診療に強く惹かれた理由です。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
ネガティブなギャップはまったく感じませんでした。むしろポジティブな意味でのギャップが大きかったです。
総合診療専攻医の研修期間中は、思っていたよりも基幹病院にいる期間が短く、多くの病院をローテートしました。
私の場合、大学病院にいたのは1年だけで、残り2年は市中病院や診療所、小児科外来など、合計5ヶ所で研修を行いました。その結果、自分が将来どんな場所で働きたいのかを自然と考えるようになりました。
すべてのローテート先が全国トップレベルと言うプログラムは恐らく存在しません。逆に言うと、どのプログラムにも強みはあります。私も総合診療専門プログラムの特徴を活かして、多様な経験をしました。そして、「自分の希望やライフスタイルに合ったローテーションが選べる」という柔軟さに大きな魅力を感じました。これはまさに、良い意味での「イメージギャップ」でした。
現在のワークライフバランスについて教えてください
総合診療科の最大の魅力の一つが、ワークライフバランスの取りやすさだと思います。働く場所や診療内容、勤務時間などを自分である程度デザインできるので、「自分らしい働き方」が実現しやすいんです。
たとえば、総合病院で外来も入院も幅広く診る、クリニックで外来のみ担当する、子育て中であれば平日週3回のパート勤務や時短勤務にする、医学教育や研究に専念する、他の本業を持ちながら非常勤で働く、在宅医療を中心に行う、開業する……など、本当に選択肢が多彩です。
そもそも絶対的に「正しい」働き方も「間違った」働き方もありません。自分にとって快適かどうかがすべてだと思います。私自身も、執筆、講演、教育活動、アルバイトと多方面で活動していますが、「総合診療が専門です」と伝えるだけで、就職も非常にスムーズです。
公的な専門医資格を得て、自由な働き方を実現できるのは、総合診療科ならではの強みだと感じています。
先生がいま考えている今後のキャリアパスを教えてください
今後はクリニックで、小児から高齢者まで主訴を問わず幅広く診療することを目指しています。また、医学生や若手医師の教育にも興味があるので、研修医と関わることのできる教育病院の関連クリニックでの勤務を考えています。
さらに、以前から海外医療にも関心があり、英国エディンバラ大学の家庭医療学修士課程をオンラインで修了しました。現在は、米空軍横田基地の病院で日本人フェローとして1年間勤務中です。将来的には、どこかのタイミングで海外での研修も経験したいと考えています。
総合診療はキャリアの幅が非常に広く、自分でもまだ知らない可能性がきっとあるはずです。「自分が貢献したい場所に応じて、自分を成長させていく」というスタンスで、今後もさまざまな挑戦を続けていきたいと思っています。
初期研修での失敗談と、それをどう活かしているか教えてください
初期研修の途中で業務に慣れてきた頃、確認不足のまま検査や治療を進めてしまい、結果的に失敗してしまったことがありました。当時は「1人でなんでもできること」に価値を感じており、つい自己中心的な診療になっていたんだと思います。
でも、診療というのは1人で完結すべきものではなく、できる限り複数の視点で意思決定をしたほうが、患者さんにとってもより良い結果につながります。この考え方は、初期研修医に限らず、キャリアを積んでからも変わらない大切な姿勢だと今は実感しています。
「誰がやったか」よりも「患者さんにとって一番良い選択は何か」を考えること。その視点を忘れずに、今も診療を続けています。
総合診療医のセカンドキャリア、将来性は?
総合診療医のセカンドキャリアは本当に多彩です。
キャリアを変更する理由はさまざまですが、総合診療はそもそも働き方が多様で、「いつ・どこで・どう働くか」を柔軟に選ぶことができます。だからこそ、興味や希望に合わせて自由にセカンドキャリアを設計できるのが大きな強みです。
私はサブスペシャリティの取得は今のところ考えていませんが、「専門がないと働けない」「何もできなくなる」といったネガティブな意見を受けたことは何度もあります。けれども、それは専門領域に特化した医師の視点であり、ジェネラリストとしての価値や可能性を理解した上での発言ではありません。
実際には、専門性を狭めるほど働き口が限定されることもありますし、競争が激しくなって生き残るのが難しくなることもあります。
どれだけバリバリ働いていても、病気や家族の事情などで、今の仕事を続けられない・・そんな想定外のことは誰にでも起こり得ます。 そうしたときに、自分の関心に合わせて働き方を変えられる柔軟性こそが、総合診療の最大の武器だと思います。将来性は無限にあり、どんな状況でも安心して一生働き続けられる診療科です。
研修やキャリアが思い通りに進まなかったとき、どう乗り越えてきましたか?
私は、学生時代から卒後9年目まで「指定された病院で研修しなければならない」という特殊な環境にありました。同級生全員が同じ病院で働く状況では、当然、すべての人にとって理想的な環境にはなりません。
「マッチングに参加したい」「もっと臨床経験を積める教育病院で働きたい」と感じながらも、自分の環境に制限があることに悩んだ時期もありました。
でも、そういうときこそ「今できる最善を尽くす」という姿勢が大事だと気づきました。
私の場合は、コロナ禍とキャリアの迷いが重なった時期に、オンラインで学べる海外大学院を探して修士号を取得したり、無料セミナーを開いて講演を続けたことで出版の機会に恵まれたりと、自分なりにできることを工夫して形にしてきました。
自由に病院を選べない人や、奨学金の縛りがある人も多いと思います。でも、「自分の最終的なゴールに近づける道を、今の環境の中で全力で探す」——そのマインドを持っていれば、きっとどこかで努力は実を結びます。
一度は「失敗だ」と思ったことも、振り返ってみれば、それが成功のきっかけだったと感じられる日が来るかもしれません。そう信じて頑張った方が、少しでも良い結果が得られると思います。 環境に左右されすぎず、自分の目指す方向に少しずつでも進んでいく——それが私のキャリアを切り拓く秘訣です。
後進の医師へアドバイスをお願いします
初期研修医の皆さんには、まず何よりも「自分の興味」を最優先にして、自分の進む道を選んでいってほしいと思います。どの道を選ぶのが正解かは、自分にしかわかりません。他人の評価や世間の常識よりも、自分の内なる関心を大切にしてください。
また、あまり「打算的」になりすぎないでほしいとも思います。「給料が良さそう」「コスパが良い」「楽そう」といった理由で科を選ぶのも一つの選択肢ではありますが、それだけで本当に長く続けていけるかどうかは別問題です。
私個人の意見ですが、医師としてのキャリアは「やりがい」「給料」「QOL(生活の質)」の3つを軸に、「その働き方を続けられるかどうか」を加えた4本柱で考えるのが良いと思っています。どれを重視するかは人それぞれで、正解はありません。ただ、4本柱をもとに、特に「自分にとって長く続けられるかどうか」を考えてみると、後悔の少ない選択ができるのではないでしょうか。
総合診療科は、給与面は施設によって差がありますが、「やりがい」「QOL」「継続のしやすさ」に関しては、間違いなくトップクラスの診療科だと思います。 もしこの分野に興味を持っていただけたなら、ぜひ仲間として一緒に働ける日を楽しみにしています。心から応援しています。
小林尭広先生経歴
- 所属:米空軍横田病院 日本人フェロー
- 出身地:北海道
- 卒業大学:防衛医科大学校
- 2016年 防衛医科大学病院・自衛隊中央病院 初期研修
- 2021年 防衛医科大学病院 防衛医大・全自・所沢連携 総合診療専門研修プログラム(2024年度専門医取得)
- 2025年 米空軍横田病院入職
コンサルタントに聞くことで開ける未来があります!