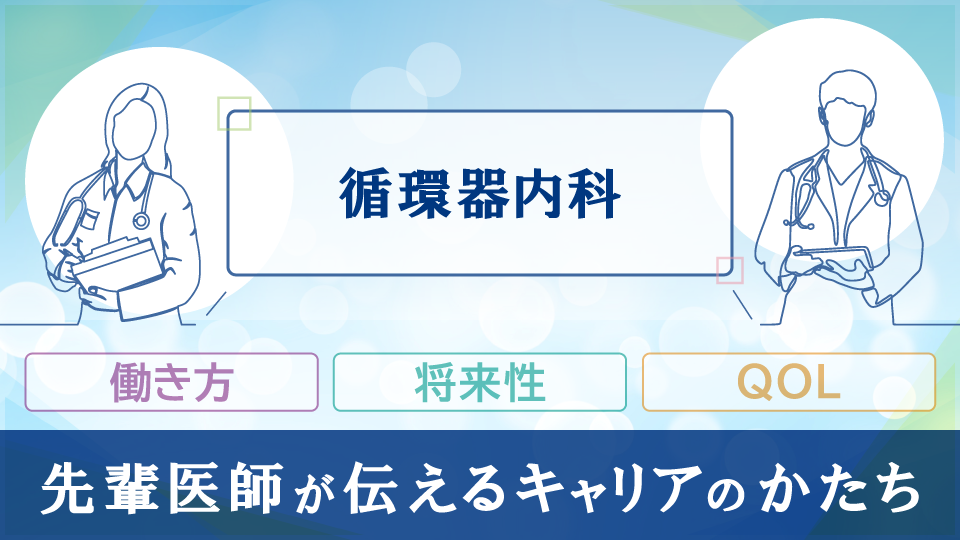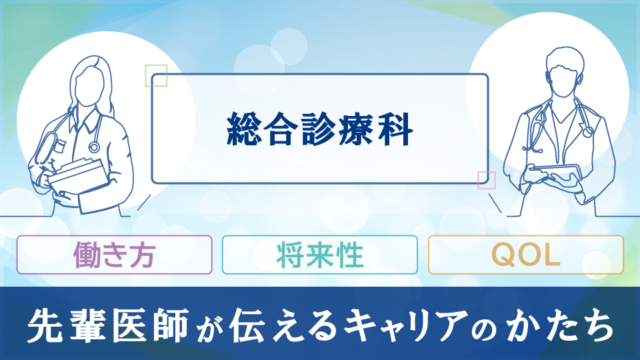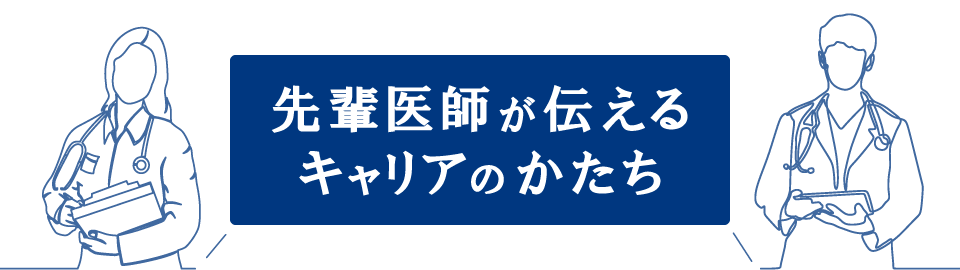
循環器診療の幅広い領域で経験を重ねながら、血管病理やAI技術にも挑戦を続ける専門医にお話を伺いました。 臨床と研究を両立し、地域医療や若手育成にも取り組む姿から、循環器内科の広がる可能性が見えてきます。
医師プロフィール/松本裕樹先生
 2012年 医師免許取得/総合内科専門医、循環器内科専門医、脈管専門医、CVIT認定医、弾性ストッキングコンダクター、下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医を保有/循環器内科の介入性と急性期・慢性期の幅広さに魅力を感じ、命に直結する医療にやりがいを実感/現在は東海大学医学部付属病院で血管病理を学びながら画像・AIとの融合にも挑戦/地域医療や若手教育にも関心を持ち、臨床・研究・教育のバランスを意識しながらキャリアを歩んでいる
2012年 医師免許取得/総合内科専門医、循環器内科専門医、脈管専門医、CVIT認定医、弾性ストッキングコンダクター、下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医を保有/循環器内科の介入性と急性期・慢性期の幅広さに魅力を感じ、命に直結する医療にやりがいを実感/現在は東海大学医学部付属病院で血管病理を学びながら画像・AIとの融合にも挑戦/地域医療や若手教育にも関心を持ち、臨床・研究・教育のバランスを意識しながらキャリアを歩んでいる
循環器内科について、どこに魅力を感じたか教えてください
循環器内科の魅力は、命に直結するダイナミズムと、患者さんの予後を大きく左右できる介入性の高さにあります。心筋梗塞や心不全といった重篤な病態に対して、迅速かつ適切な診断・治療を行うことで、数時間のうちに患者さんの状態が劇的に改善する瞬間を何度も経験しました。
また、画像診断やカテーテル治療など多岐にわたる手技・技術を習得できる点も、成長意欲のある方には大きなやりがいとなるはずです。慢性疾患との付き合いもあり、急性期と慢性期の両方をバランスよく診られることもこの分野の強みです。
入職前と入職後のイメージギャップはありましたか?
循環器内科と聞くと、どうしても「忙しい」「ハード」といったイメージが先行しがちですが、実際に入ってみると、むしろチーム医療の素晴らしさや先輩方の丁寧な指導に支えられて、確実にステップアップできる環境だと感じました。
もちろん当直や緊急対応もありますが、その都度、自分の判断力と技術力が磨かれていく感覚があります。単なる技術職ではなく、患者さんの背景や家族の思いもくみ取る総合力が求められる点で、「医師としての力」を本質的に問われる科だと思います。
現在のワークライフバランスについて教えてください
循環器内科はハードな面があるのは事実ですが、ここ数年で働き方改革が進み、シフトの調整やタスクシェアが整備されつつあります。私自身も家庭を持つ身として、子どもの行事や通院などに配慮してもらえる環境で働いています。
オンとオフをしっかり分けることで、むしろ仕事の集中力も上がりました。仕事に没頭するだけでなく、子育ても積極的に参加できており、家庭での立場は保てております。
先生がいま考えている今後のキャリアパスを教えてください
現在、私は東海大学医学部付属病院 循環器内科にて、血管病理の専門的な知識を深めるため、国内留学中です。これまで臨床の第一線で培ってきた治療技術や判断力に加え、病理学的な視点を得ることで、より本質的な疾患理解と的確な診療判断を可能にしたいと考えています。
今後は、この経験を地域医療や若手医師の教育、そして重症下肢虚血などの末梢血管治療に活かし、より多角的な診療を実践していく予定です。さらに、病理と画像・AIの融合といった新しい領域にも挑戦し、臨床・研究・教育のバランスがとれたキャリアを目指したいと思っています。
初期研修での失敗談と、それをどう活かしているか教えてください
初期研修医時代、心不全患者さんの尿量モニタリングを甘く見てしまい、脱水を悪化させてしまったことがあります。その時、上級医から「循環器の基本は“出入り”の管理だ」と教わり、今でもその言葉を大切にしています。
失敗を通じて、患者さんの変化をこまめに観察し、小さなサインを見逃さない姿勢が身につきました。現在では、若手に同じような経験をしてもらわないよう、失敗談も含めて伝えることを心がけています。
医局人事で向き合ったことや、医局員ならではの経験を教えてください
医局人事では、希望とは異なる赴任先に配属された経験もありました。当初は不安もありましたが、地方病院での勤務を通じて、幅広い疾患を一人で対応する力、他職種との連携、そして地域住民との信頼関係の築き方など、大学病院では得られない経験を積むことができました。
大事なのは「与えられた環境で何を得るか」という前向きな姿勢です。医局のネットワークや教育体制のおかげで、どこにいても安心して学び、働くことができたのは大きな財産です。
後進の医師へアドバイスをお願いします
今、医師の世界は静かに分岐点を迎えています。高度な技術や収益性の高い領域に人気が集中する一方で、命の瀬戸際に立つ現場──たとえば循環器内科や救急医療の分野では、担い手が年々減り、現場が疲弊し始めています。
心筋梗塞で倒れた人を助ける、重症心不全の患者を救命する、失われかけた血流を末梢までつなぎとめる──こうした「目の前の命に真っ向から向き合う医療」は、他では得られない充実感と責任感があります。
循環器内科は確かにハードな側面もありますが、その分、医学の進歩やテクノロジーの導入も進んでおり、チーム医療や働き方改革を通じて「長く続けられる仕組み」も少しずつ整ってきています。
皆さんに伝えたいのは、「きついからやめておこう」ではなく、「きついからこそ、自分が必要とされる」ということ。患者さんの命を預かる現場には、まだまだ人の力が必要です。一緒に、医療の土台を支える側に立ってくれる仲間を、心から待っています。
松本裕樹先生経歴
- 所属:東海大学医学部付属病院、循環器内科
- 出身地:岩手県盛岡市
- 卒業大学:岩手医科大学
- 2012年 岩手県立久慈病院初期研修、岩手医科大学社会人大学院入学
- 2013年 岩手医科大学内科学講座循環器内科分野入局
- 2016年 岩手医科大学 大学院卒業
- 2022~2024年 岩手県立大船渡病院循環器内科長
- 2024年4月から国内留学にて、東海大学医学部付属病院へ所属
コンサルタントに聞くことで開ける未来があります!